「Mutoys島 本の祭典2020(冬)2日目」
開催おめでとうございます〜・:*+.\(( °ω° ))/.:+
最初、薄い本を売ろうと考えていた隠れ作家(LV7)のとりぽやです。
それっぽい祭典のそれっぽい薄い本にはそれっぽいお話が載っているものですよね。いちぶのおにいさんおねえさんに需要があるのですよね。
知ってる。
だから申請書の裏にそれっぽい原稿をこっそり書いておりましたが、妖精さんに怒られました。
妖「売りものの申請書にラクガキしないでよ〜しかもそれっぽいこと書いたら島の掟に反して神罰がくだるわよ〜」
と「ごめんなさい〜。゚(゚´ω`゚)゚。全年齢対象にするから〜。あとちゃんと紙束に書くから〜」
妖「紙束も売りものだからだめ。セクレタリにでも置いてくるがいい」
というわけでここで頒布することにいたしました。
永遠に結ばれることのないしょうじょと妖精さんの、ほんのり百合っぽいベリーショートストーリーです(*´ω`*)
1287字(2分で読めます)
※二次創作の苦手な店主さんは、閲覧にはご注意願います。
※ ※ ※
※ ※ ※
永久凍土
耳が痛むほどに静かな夜もある。
きっと、聞きたくないことを聞かないために、聞きたいことだけを聞くためにだ。
月明かりに青白く光る雪原のうえ、ひっそりと建つ山小屋の軒下に、少女と妖精が向かいあっている。少女は冷えた手指を擦りあわせ、妖精は背中の羽を広げたまま地上からわずかに浮いている。羽音はしなかった。
山小屋のなかでは引越し準備がおこなわれていた。店主があれやこれやと指示を出し、倉庫妖精たちが慌ただしく荷造りをしている。もうすぐ、月の傾くころには彼らは遠い街へと移ってしまう。
「ほんとうに行ってしまうのね」少女は次の街の名前を聞かなかった。「さみしくなるわ。また、帰ってくる?」
「うん」妖精はやさしくほほえんだ。
(うそつき)少女にはわかっていた。妖精の主人である店主は、街から街へ移動しながら宝石の採掘をなりわいとする鉱夫であり、すでに掘り尽くしたこの街には、もう用はないのだ。
「わたしも、おとなになったら鉱夫になろうかな、と考えたの。どうかしら」
「うん。すてきね」
妖精はやさしく同意した。羽を閉じて雪のうえに降り立ち、少女へ一歩近づく。さくさくとちいさく雪がくずれて、それが妖精の重さのすべてだった。人ではない者の、悠久の時を生きる者の、存在のすべて。
「おとなになったら鉱夫になって、島中をめぐるの。トパーズ村で黄玉を掘って、アメジスト街では紫水晶を。そして、いつか…」少女は夢見るように、かじかんで赤くなった両手を大きくひろげた。
妖精にはわかっていた。少女は少女を全うし、この街で老いてゆく。出会ったばかりのころは魔法のステッキをふりまわしていたおじょうちゃんが、いつのまにかアクセサリで着飾るしょうじょになり、やがて静かに本を読むおねえさんになり、生活道具を買い漁るおばさんになり、最後は木の杖をついて歩くおばあさんになる。鉱夫になることは決してないのだ。
「わたしも、いつか…いつかね…」
やり場をなくしたままぼんやりとひらいた赤い手を、妖精のしろい指がそっとつつむ。今はうなずいてあげることしかできない。
「うん。いつかね」
自分が人間だったらこの手をはなさず、この羽を彼女のためだけに羽ばたかせて、島中をめぐることができたのだろうか。でも自分は店主のための販売妖精であり、ほかの生き方を知らない。住民の時間はあまりに早く、その一生はあまりにも儚い。もしも再びこの街に戻ってくることがあったとしても……
妖精は思わず、少女の手を離した。
傾きかけた月を薄い雪雲が覆いはじめ、粉雪の舞うかすかな気配がふたりに近づいている。音はしなかった。
「また、会えるかしら」少女はもう一度尋ねた。彼女の声は震えていたが、寒さのためではなかった。その瞳につよい光を宿し、まっすぐに妖精をみつめる。泣くのを堪えているときの癖だ。島中の宝石をあつめたロイヤルジュエリーにも匹敵する、この気高い輝きを、妖精は決して忘れることはないだろう。
「うん、また会おうね。いつか」
くっきりとした声でそう告げた。永久凍土のように溶けない嘘が、少女の耳にやさしく残ればいいと願いながら。

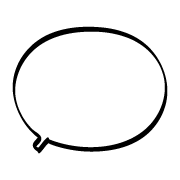


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です