SO2二次創作。
おじいさんとしょうねんの、とある冬の一日の物語です。
* * *
* * *
おじいさんへの地図
最後の手紙を書き終えて、どうやらそのまま寝てしまったようだ。夜明けの寒さがいっそう身にしみる。なんにせよ、紙束とペンが足りてよかった。今年こそ早く終わらせようと思うのに、毎年ぎりぎりになってしまう。
木の扉が勢いよくひらいて、ひだまりのような少年が飛びこんできた。「おじい、薬だよ」と薬湯入りの湯飲みを机に置く。
「またここで寝ちゃったの? そんなだから風邪が治らないんだ。もう歳なんだから養生しなきゃ」ぶつくさ言いながらカーテンを開け、床に落ちた膝かけを拾いあげてたたむ。くるくるとよく働く自慢の孫だった。
「伝説の錬金術師の薬だよ、さっき行商に来てたんだ。高かったけどよく効くそうだよ」
「自称伝説ではないのかのう」
おじいさんは湯飲みに口をつけて渋面をつくる。「さすがは伝説じゃ、すああまを砂糖水でふやかしてメィプルシロップをかけたような味じゃな」
少年は卓上の手紙を取り、「これでぜんぶ?」てきぱきと仕分けてゆく。ルビー街、ルビー街、エメラルド街、トパーズ村、アジト跡地……こっちはオパール街。手紙の束をとんとんと揃えて、木箱に入れた。なかにはもっとたくさんの手紙と、包装紙にくるまれた大小さまざまな箱がある。
「甘くて飲みやすい薬だって言ってたよ。治らなかったら困るのはおじいじゃないんだ。わかってるでしょ。袋詰めはやっとくから、おじいは着がえて準備して。早くしないと夜になっちゃうよ」
木箱をかかえて少年が出てゆく。おじいさんはやれやれと激甘風邪薬を飲み干した。長い一日となりそうだ。
その夜遅く、おじいさんが仕事から帰ってくると少年はまだ起きて待っていた。遅くなるから先に寝ているよう言ってもいつも待っている。その理由がおじいさんにはわかるので、その日はいっそうつらかった。親が生きていればこんな森の奥に年寄りと暮らすこともなく、街の学校で友達もたくさんできただろうに。それでも「おじいと暮らす」と言ってくれた孫の気持ちが嬉しかった。せめてこれ以上さみしい思いはさせたくないものだ。
「おじい、今年はどんな子がいたの?」少年は外の話を聞きたがる。物心ついてからこちら、ほとんど森を出たことがないのだ。毎週通ってくるパン屋と行商人、たまに現れるあやしげな錬金術師や勇者、稀に迷いこんできて一宿一飯を乞う旅人。この子の世界はそんなものだ。今は、まだ。
おじいさんは少年を暖炉のそばに招きよせた。できるだけ居心地のよい空気をつくってやる。温めたミノ牛乳にドゥーナツとキャンデー、ふかふかの抱きメィクラと清潔なパージャーマー。ランプの明かり。薪の爆ぜる音。おじいさんは話しはじめる。
「最初はブルー街じゃ。木の剣をほしがっていたおぼっちゃんは足の悪い子じゃった。剣をにぎると勇気が湧くと言っていたのう」
「木工師に頼んだ木刀だね。あれはかっこよかったもの」
「ガーネット街のおじょうちゃんは、絵本じゃ。去年までずっとお菓子だったのじゃが、なるほど、文字が読めるようになって嬉しかったようじゃな」
「きれいな顔料の本だったから、きっとよろこんでくれるね」
「ギルド街のしょうじょは剣市への地図を。どんな勇ましいしょうじょかと思ったが、まだまだあどけなかったのう」
「セレブセットをほしがっていたおねえさんは?」
「ミミ星人街じゃな。あんな高級品を頼まれるとは思ってもみなかったわい」
「だから色石のブローチにしたんだね」
「うむ。少し残念そうじゃったがの。さすがに予算おーばーじゃ」
贈り物の袋詰めを手伝ってくれるようになったのはいつからだったか。今年はほとんどこの子がやってくれた。ひとりひとりに宛てた手紙を添えて、リボンをかけ、配る街ごとに仕分けして。それを受け取る人の喜ぶ顔を見ることはないのに。今は、まだ。
「おいで」
おじいさんは少年を膝のうえに抱きあげた。その重さにあらためて驚く。この子もいつまでも小さなこどもではない。そう、今はまだ。でも、いつかは。
「来年は、いっしょに行ってみるかね?」
少年は目を輝かせて祖父を見る。「ほんとう?」
「ほんとうにいっしょに行っていいの? ぼくもプレゼントを配っていいの?」
「わしに弟子入りすると決めたんじゃろう?」
親を亡くしてから多くのことをあきらめてきた小さな手。その手がひとまわり大きくなって、おじいさんの両手をつつんだ。
「うれしい! もちろんだよ。ぼく、おじいの跡を継ぎたい、ぜったい自慢の弟子になる。がんばるよ」握られた手がぶんぶんと上下する。
「では、自慢の弟子にこれを渡しておこうかのう」
おじいさんの白い仕事袋に、贈り物の箱がひとつだけ残っていた。稀なことではあるが以前にも、受け取り主が亡くなって配達できないまま持ち帰られた荷物はあった。しかしこれは見慣れない包装紙……少年が詰めたものではない。
少年は思い出していた。ひとりぼっちになったあの日、遠くの街から迎えにきてくれたおじい。おじいが作ってくれた木のおもちゃ、焼いてくれた甘いお菓子。やさしかった。なのに一年でいちばん大切な日に、一晩中待っても帰ってこないおじい。
そのわけを知ったとき、少年は胸に決めたのだ。ぼくももらうだけじゃなく、あげるひとになりたい。おじいのように。
箱のなかからはド派手な色のふわふわ帽子ともこもこブーツが現れた。老人は孫の頭に手を置く。
「誕生日おめでとう。お仕事入門セットじゃ。わしの大切なおまえに」
真っ赤な帽子をそっとかぶせてやる。戴冠式のように恭しく。そのまま顔の半分をすっぽりかくして少年はつぶやいた。「ありがとう」しばらくそうしていてからようやく顔をあげた。真冬の太陽がそこにあった。
「でもおじい、帽子と靴だけだよ。服はどうするの」
「すまんな。それも予算おーばーじゃ。なあに、来年の今時期までには裁縫師に頼んで作ってもらうさ。伝説のな」
少年はその夜、というよりも明け方近くなってから、ふわふわもこもこの夢を抱きしめて眠りについた。新品なのになぜか懐かしい香りにつつまれて。
おじいさんは腰をあげ、一日ぶりにベッドへ向かう。実はブーツのなかにこっそり手紙を隠しておいたのだが、孫はいつ気がつくだろうか。
一晩中かけて書きあげた長い長い手紙。少年はやがて知るだろう。師から弟子へ代々伝えられるこの仕事の秘訣、心構え。そして大切な人を大切に思う気持ち。それは一年に一度、世界中のひとに幸せをふりまくおじいさんになるための、きっと明るい道しるべになることだろう。
「さて、新しい一年のはじまりじゃ」
(おしまい)
* * *
お話のなかに公式品をだいたい21個入れました。
暇つぶしに探してみるもよし(*ˊᵕˋ*)
はぴめり〜〜〜♪

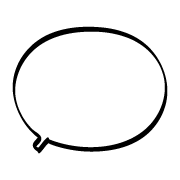



 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です