「そっちそろそろ終わったー?」
「はーい!少し休憩してまた頑張りまーす!」
そういってシルヴィエはたった今書き上げた申請書にミスがないかを確認し、それを完成品ファイルのあるサイドデスクに仕舞い込み軽く背すじを伸ばした。
「シルヴィエちゃんも仕事終わったの?なら丁度いいわ、これから私達お茶会なの、ご一緒しましょう!今回は店主さんがくれたクッキーもついてくるわよ!」
先輩妖精であるアリーはいつも作業の合間合間には話しかけてきて、新人であるシルヴィエにお茶のお誘いをかけてくる。当初はシルヴィエも歓迎されているのだと喜び勇んで参加したものだが二回目以降から店主の余ったハーブティーをずっと飲み続けているのだと知ってからは遠慮させてもらっている。
「ごめんなさいアリーさん私今回もちょっと…」
「そんなこと言わないで、ほらこのクッキー新しい物よ。シルヴィエちゃんはいらない?」
そういってアリーはまだ暖かさを残し、甘い匂いを漂わせるクッキーの乗った皿を差し出してくる。本来妖精たちの休みや食事は役所から与えられるもので、このような嗜好品が与えられることは少ない。ハーブティーは以前淹れた物を温めただけのものだがこのクッキーは違う。恐らくは店主が店頭に並べるために買ってきたものだろう。
「…じゃあ、ちょっとだけ」
妖精は甘いものが好き。シルヴィエだってそれに反することはないのだ。
「ああもう!」
ティーセットとクッキーをもって中庭に移動していた時店主の机を叩く音にビクリと背筋が震える。
ここの店主は気難しい人のようでいつも他の店主さんと相談したり、販売妖精達と何かのアイテムの値について相談しては癇癪を起している。シルヴィエは以前のお役所の仕事をクビになり、そこをこの店主に拾われた口だったのだがまさかこんな人だとは夢にも思わなかった。あの時この世に絶望したシルヴィエを心配して手を差し伸べてくれた店主はどこの誰だったのだろう。
「店主さん今日も必死に考え込んでるのね。私ちょっと行ってくるわ、先に待っててシルヴィエちゃん。クッキーいくらか食べちゃってていいから」
昔からここに勤めているアリーは困ったような表情をしてこちらにクッキーを渡して飛んで行った。シルヴィエは投げるようにして渡されたクッキーを慌てて受け止め、一人中庭へと向かった。
「なーんで私こんなことしてるのかなあ」
シルヴィエは一人溜息をつき、どうにもうまくいかない自分の現状を嘆く、妖精学校を卒業し、エリートとしてお役所で働く事になった当初は家族総出でお祝いをするような事もあったというのにシルヴィエの今の現状ときたらどうだ。お役所で働いて一か月もせずに上司とつまらない言い合いが原因で集中力が切れ、本当にくだらないミスを重ね、気づけばお役所の掲示板に暴言を書いてクビになっていた。
今になって考えてみればあの上司も仕事のアドバイスをくれただけに過ぎなかった。私はエリートだという意識が先行していただけにすぎなかった。自分の周りの妖精が気まぐれ妖精として生きるような者ばかりだったのでお役所に入った当初、自分は世界の頂点にいる妖精だとばかり思い込んでいたのだ。
「おーいシルヴィエちゃーん。今日は店主さんも一緒にくるんだってー」
アリーの綺麗な高い声が中庭に響き、数人の妖精と一緒に店主が顔を出した。店主はくたびれたYシャツに黒のスラックスを着て、手には二本のボトルと数枚の紙を持っていた。
「聞いて聞いて、今日はいつものハーブティーじゃなくて店主がとっておきの飲み物を出してくれるんですって!」
そう興奮した声でアリーが述べてくるのと同時に、シルヴィエは疑心が先に出ていた。
本当は妖精にこのような贅沢をさせる義務は店主たちにはない。妖精たちの給金や報酬は役所から支払われるもので店主たちに課された義務は販売勢や事業税を出すことだけなのだ。さっきまで机を叩いていたような人物がこんなに優しいはずはない。
「何?難しい顔してるの?シルヴィエちゃん。ほら、お茶会よ。折角なんだし楽しみましょう!」
店主はここよー。とアリーがお茶会の準備を整えると他の販売妖精達や倉庫妖精たちも巻き込んで賑やかなお茶会が始まった。
お茶会は賑やかなままに流れ、新米であるシルヴィエには他の妖精達からの質問が飛んできた。なんでここに来たの?どこから来たの?好きな食べ物は?というような事から始まり、終わりには家族の事まで質問攻めにされた。シルヴィエは質問攻めにされて右往左往している中で他の妖精たちの自己紹介や仕事中の愉快な話を聞いてこの職場で楽しくやっていけそうだと思っていた時、シルヴィエが本来警戒していたそれはやってきた。
「シルヴィエ、今日の仕事はどうだった?」
今まで微笑んでこちらの事を見ていた店主がシルヴィエに質問を投げてきたのだ。
「きょ、今日のお仕事ですか?ええと……」
正直なところ今シルヴィエに任されている仕事は誰でもできるような申請書の規定をそのままコピーするだけのものでどうこういえる作業成果や感想は存在しないのだ。
「これ、シルヴィエが書いたものだよね?」
シルヴィエが答えを言い淀んでいると店主は懐から持っていた紙を取り出しシルヴィエの前に突き出した。先ほど書き上げた申請書の一枚だ。
「あっ……」
シルヴィエは答えに詰まった。役所での一幕が頭をよぎったのだ。シルヴィエが確か、簡単なコピー作業を任されて、くだらない誤字をしてしまい上司ともめる切っ掛けになったあの事件。あの時からシルヴィエは周りと折り合いが悪くなり、すべてがうまくいかなくなった。もしかしたら今度もまたそうなるのかとシルヴィエは思わずそれに手を伸ばした。
「シルヴィエは綺麗な字を書くね。僕なんかよりもよっぽどいい」
恐怖にかられて手を伸ばしたシルヴィエを他所に店主はとても感心した顔でその申請書を見ていた。その顔は一点の嘘偽りもなく、シルヴィエが怖がるようなミスの指摘などでもなかった。
「あら本当ね。前店主さんが真似て書いたのとはえらい違い」
アリーがその申請書を覗き込み、他の妖精たちもそれに続く、次々に綺麗ねー。本当ー。といった声が続き、シルヴィエは思わず「え」という拍子の抜けた声を出した。
「シルヴィエ、今の仕事が終わったらこれ使って皆で休暇でも取ろうか。折角なんだから歓迎会もちゃんとしないとね。」
申請書を妖精たちに渡し、店主はそういってシルヴィエに微笑みかけ、手に持っていたポンジュースをコップに注いでシルヴィエに手渡した。
「はい!これからよろしくお願いします!」
さっきまでの不安もなくなり、活力に満ちた顔でシルヴィエはそう答えた。
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
【SO2二次創作イベント】作業妖精シルヴィエのお話
関連投稿
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 住民売り考察日記70 V/P比の差と選択割合についてhaguruma / 1820 view
住民売り考察日記70 V/P比の差と選択割合についてhaguruma / 1820 view -
 肉屋Lv.9を目指すならリンファ / 2060 view
肉屋Lv.9を目指すならリンファ / 2060 view -
 住民売り考察日記㊾派生連鎖レシピの付加価値倍率減衰グラフ(6~10段目)haguruma / 3103 view
住民売り考察日記㊾派生連鎖レシピの付加価値倍率減衰グラフ(6~10段目)haguruma / 3103 view -
 住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3021 view
住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3021 view -
 住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3101 view
住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3101 view -
 「商品の価値を推し量る一つの方法」或る酪農家の手記ハレルヤさん / 4737 view
「商品の価値を推し量る一つの方法」或る酪農家の手記ハレルヤさん / 4737 view -
 レポートのすゝめ村雨堂 / 5667 view
レポートのすゝめ村雨堂 / 5667 view -
 販売経験値活用のススメてぃー@骨のひと / 7998 view / 1
販売経験値活用のススメてぃー@骨のひと / 7998 view / 1 -
 Yossiと行くアイテムの作り方講座~初心者編~yossi8382 / 5989 view / 2
Yossiと行くアイテムの作り方講座~初心者編~yossi8382 / 5989 view / 2
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 住民売り考察日記70 V/P比の差と選択割合についてhaguruma / 1820 view
住民売り考察日記70 V/P比の差と選択割合についてhaguruma / 1820 view -
 肉屋Lv.9を目指すならリンファ / 2060 view
肉屋Lv.9を目指すならリンファ / 2060 view -
 住民売り考察日記㊾派生連鎖レシピの付加価値倍率減衰グラフ(6~10段目)haguruma / 3103 view
住民売り考察日記㊾派生連鎖レシピの付加価値倍率減衰グラフ(6~10段目)haguruma / 3103 view -
 住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3021 view
住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3021 view -
 住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3101 view
住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3101 view -
 「商品の価値を推し量る一つの方法」或る酪農家の手記ハレルヤさん / 4737 view
「商品の価値を推し量る一つの方法」或る酪農家の手記ハレルヤさん / 4737 view -
 レポートのすゝめ村雨堂 / 5667 view
レポートのすゝめ村雨堂 / 5667 view -
 販売経験値活用のススメてぃー@骨のひと / 7998 view / 1
販売経験値活用のススメてぃー@骨のひと / 7998 view / 1 -
 Yossiと行くアイテムの作り方講座~初心者編~yossi8382 / 5989 view / 2
Yossiと行くアイテムの作り方講座~初心者編~yossi8382 / 5989 view / 2

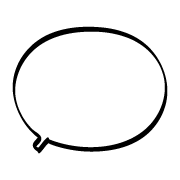


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です