
わたしお店開いたの、と久し振りに会った友人から告げられた。
聞けば妖精の住む島で勇者業をいとなみつつ、そこで得た珍しいものを持って帰り、人々に売っているらしい。
妖精さんと女子会もするよ、とにっこり笑う彼女の笑顔がまぶしく輝く。
ふとそんな暮らしもいいなと思った。
思うように、自由に、ちょっと不思議な島でのんびり暮らす。
かねてから湖畔に別荘を建ててのんびり釣りでもしながら過ごしたいとは考えていた。
機会がないままここまできてしまったが、彼女も店を開いたばかりだというし、いっしょに新しい生活をはじめてみるのもいいかもしれない。
「ぼくもその島へ引っこそうかな」
「あなたも来るならうれしいな」
先に移り住んだ彼女がいれば心強かった。
ほどなく、友人の店から徒歩圏内の、近くに川が流れる緑豊かな森に小さな家を構えた。
新緑が鮮やかに芽吹き、川の水は澄んで冷たい。
心地よい風を感じながら、近所の地図を手に森を散策した。
家の周りの木々は秋には色とりどりに色づくだろうし、その落ち葉を踏んで歩くのも楽しそうだ。
散歩をしていると料理や薬に使える薬草や小枝、硬い石ころやキラキラと光るきれいな川砂が目にとまった。
それらを集めてきて、そのつど島の通貨と交換してもらった。
近所の地図が買えるだけ溜まったら地図を買い、また薬草を拾って歩いた。
そうやってしばらくは近所を散歩しながらゆったりとした時間の流れを楽しんでいたが、なんとなく生活にハリがないなとぼんやりする時間も増えたころ、あることに気づいた。
まわりに人家がいくつかあることを知っていたが、そのどれもがどうやらなにかしらものを売る店であるのだ。
避暑地の別荘での休暇のように遊びほうけているのは自分とうちの妖精たちくらいなようだった。
たしかに本腰をいれてここで暮らしていくならまとまったお金が必要になってくる。
なにかしら売り買いして生活費を稼ぐ必要があるなと思った。
その日暮しはもう十分満喫した。
いまではもっとこの島の人々とふれあってみたい気持ちが強くなっていた。
手元にあった少ないお金を握りしめ、近くの店の扉を開いた。
白くてひやりとする小さな乳鉢をひとつ買って帰り、色草をすり潰した。
自分も妖精たちも顔や手をどろどろに汚してなかなかたいへんだったが、なんとか顔料を作ることができた。
これで、いままで紙のまま売っていた白い用紙に自分で地図をえがける。
できることが増える。
そのわくわくは久し振りに感じる高揚感だった。
「今日はじめて地図以外の買い物をしたよ。なにを買って、なにを作るのか自分で決めていいんだね。楽しいね」
うれしくなって友人に報告をしにいった。
「うん。そうやって経済をまわしていくの。お店が増えていろんなものが売られれば、ひとが増えてますますにぎやかな街になるね」
友人はおめでとう、と言って冷たいハーブティーを出してくれた。
それは少し苦くて、とてもおいしい味がした。
創業70日 春立ハウス
オーナー番号 #32873

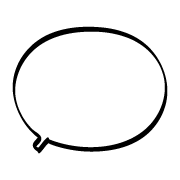




 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です