窓から差し込む柔らかい太陽の光が、深い眠りから覚醒へと誘う。
ベッドから抜け出し、窓を開く。そよぐ風が肌を撫でてきて、心地いい。
小鳥が囀り、こちらに向けて朝の挨拶を交わしてくれているかのよう。
今日もいつも通りに、気持ちのいい朝を迎えさせてもらえる事に感謝をしながら、傍らの机にそっと置いていた仮面を顔に被せた。
「よし、今日も頑張ろうか」
と呟いた途端、ドアを叩く音に部屋の空間を支配された。
「マスター! 起きやがれ! 朝だぜ!」
「……」
そう、静かな時間はこの時をもって終了したのだ。
「早く起きねぇとこっぺぱんが冷めちまうんだぜ!」
お決まりのセリフと共に、バンッと扉が開いて小さな影が飛び入ってくる。
その小さすぎる体に、あれだけの大きな扉を思い切り大きな音を立てて開ける力があるのだろうかという疑問の答えはとうの昔に投げ捨てていたが、折角の静かな時間に水を差す行為に苦言を呈した。
「起きとるわい。朝ぐらい静かに出来んのかお主は」
その叱責も相手は悪いとは全く思っている訳もないその子は目前で忙しなく飛び回ってくる。鬱陶しいとは思わないが、やはり邪魔だ。
そしてもう一人、同じような小さな体格で長い髪を三つ編みに結わえている子も部屋の中にそっと入ってきた。
「マスター、おはようです」
「おはようペルカ。で、後ろに持っているそれは何なのじゃ?」
「とっておきです」
ニコニコとするペルカは、叩くとピコピコと音がするハンマーを手にしていた。毎朝何かしら所持してくるので最近はあまり気にしなくはなったが、恐らく寝坊をしていたらあれでしばかれているのだろう。しかも侮っていたら地味に痛いのだ。
(ちなみに今までで最も血の気を引いたのは鍛冶ハンマーだ。)
「朝ごはんにするです。コルトはさっさと着替えてくるです」
「へーい!」
ペルカは未だに寝間着姿だったコルトに普段着を渡した後、今度はこちら側に向かってのたまった。
「夜中の作業の確認、よろしくですよマスター」
寝ていないわけではないだろうが、いつもいつも夜中までお疲れ様ですありがとう。
くるりと見せてくるペルカの背中は、小さいながらも頼もしく感じたのだった。
☆★☆★☆
街の中心部から伸びる比較的新しく出来た街道は深い森の中へと続いていて、我らが工房もその街道沿いにある。
普段はポーションや魔法の知識を詰め込んだアクセサリーの製作をメインに、片手間に杖の作り方という本を執筆、というごくありふれた錬金術と作家業で生計を立てている。
作業を終えたポーション類などが棚へとキレイに陳列されていて、客を迎え入れる準備は整っていた。
「相変わらず仕事の手際が良くて助かるのぅ」
「それはありがとうですよ。あ、マスター。そろそろ薬本と乳鉢、それとペンと紙束の補充手配、お願いしたいです」
注文書を手渡され、早速とペンを走らせようとしたのだが……
「ん?」
端の方に走り書きされている文字。
字の汚さから、コルトが頑張って書いた字だというのは想像に容易いのだが、その内容に引っかかりを覚えた。
『コッペパン1000本、ソーセージ1000本、ミノチーズ500個にキャベツ1000玉……』
特別な素材というわけではないが、如何せん数が多い。
「ペルカ。これは一体何じゃ?」
「はい? ……ああ、これはわたしとコルトが二人で計画しているものに必要だった材料なのです」
「計画?」
「そうです。計画です」
「……」
普段から表情は豊かなペルカではあるが、今の彼女の表情は明らかに普段のものではない。
恍惚な、かつだらしない笑顔。その二言が何故か当てはまってしまう、そんな表情。
「着替えてきたんだぜ! ……あ、そのメモ!」
普段着と愛用の帽子を身に着けたコルトが肩の上に座り、持っていたメモを奪ってくる。
そしてペルカ以上にだらしない笑顔を浮かべて言う。
「あー、楽しみだぜぇ……もうあと数時間で出来上がるんだったよな、ペルカ」
「はいです。後1時間とちょっと。ちょうど開店時間前に間に合いそうです」
何も聞かされていないが故に、心の中に沸々と湧き上がるのは一抹の不安。
普段から商品を食べてしまうなどのイタズラ好きなコルトと、普段はしっかりものでも時々抜けてしまうペルカの二人の様子に、その感情が大きくなるのだ。
「……お主ら。ワシに隠し事をして一体何をしでかしたのじゃ?」
「しでかしただなんて言葉が悪いんだぜ、マスター」
「そうです、前から計画していた崇高な計画は、例えマスターでも邪魔は許しません」
言葉だけは中々にアグレッシブである。その表情さえなければ恐れ慄いたことだろう。
工房内の作業や材料集め、更には店番を一手に引き受けてくれるこの二人を怒らせることは即ち、己の死に近しいことと同義なのだ、その表情さえなければ。
「た、頼むからせめてワシの迷惑にならんように頼むのじゃ……お願いじゃから……」
その切実な願いは、果たしてどうなることであろうか。
侮るなかれ。この二人はそれなりの頻度で予想斜め上を飛び越えてくれるのだ。
大きな不安を胸に、その計画完了までの時間を片手間の作業をしながら、過ごしていくことになった――
☆★☆★☆
その時はやってきた。
あまり仕事にはならなかった数時間、ずっと抱えていた心配を目の前にして思ったのだ。
ああ……あの魔物が襲ってくることが、現実になってしまった、と。
「ペルカ。準備は良いんだぜ?」
「勿論です、コルト」
目に飛び込む光景はあまりにも凄惨だった。
具材を挟むための切り目から生まれたパン粉、匂いからして恐らくソースとして使用した大量のミノチーズの残滓、使うことのなかったキャベツの芯や固くなった外側の葉、どのようにして刃毀れしたのか聞いてみたいナイフ達、仕上げに使ったであろうマスタードの黄色とケチャップの赤……それらが見るも無残に散らばり、厨房の中は阿鼻叫喚状態だ。
沢山の石窯の前に更に並んだ、何らかの力で包まれたソレらに、コルトとペルカは手を伸ばした……そして――
「うわーい! すげぇ!」
「やりましたです! 一度やってみたかったのです!」
次から次へと何かが姿を表し、部屋中一杯に積み上がっていくその様。
そう、この子達が内密に進めていた計画とは……
「……どうするのじゃ、これは……ッ! 全部食いきれるわけないじゃろうッ!」
好物であるこっぺぱんから調理した、ホットドッグの山を作ること。
たったそれだけのことだ。
工房内に物を置ける許容範囲を犠牲にして……
どこからともなく飛んでやってきた、青い鳥がその山のてっぺんに降りたち、嬉しそうなコルトとペルカを眺めているようだった。
が、ワシにとってはこれからこのホットドッグをどう捌いていくのかを考えていくという、憂鬱な時間の幕開けとなったのだった。
お粗末!


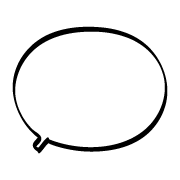


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です