一人で品物を運ぶのは孤独でさみしい。たまに人を見かけて声をかけるが多くの者は行き先も違うので長くは話さない。孤独の時間が旅のほとんどを占めている。
代り映えのない景色を見ながら飛んでいると前に輸送妖精がいるのを見つけた。久しぶりに妖精を見つけた喜びもあって速度を上げてみると後姿から女性らしい。
「こんにちは、どちらまで?」
「こんにちは、バトル街まで行きます」
見たところ大きな荷物はない。
「これは珍しい、私もバトルへ向かっているところなんですよ。バトルの砂を買われに?」
しばらくの間は旅仲間ができるであろうことに胸の中の孤独感が消えて喜びが広がっていく。
彼女は笑って、
「はい、みんなそういいますね。ふふ」
「はは、仕方のないことですよ、バトルは砂の一大産地ですからね。」
「バトル街の他に大きな市場はないので島の反対側から毎日買いに行かされて参っています」
彼女は苦笑しながらそう答えた。
「はは、わかります。うちの店主も王国の輸送ランキングに乗るんだと言って店の仲間と話す暇もなくて困ってますね。どうです、バトルまで一緒に行かれませんか」
「ぜひ」
俺は輸送妖精には向いていないと思う。
バトル街の人口は王国で一番低いこともあって街とは言うが砂ばかりが広がり殺風景で少数の住民が舗装された道を歩いていなければ街だとは気づくまい。道中、彼女とはお互い店主の愚痴が多めの他愛無い話をして気づけば目的地に着いていた。名残惜しく思いながら、
「ここでお別れですね」
「はい、また会えるといいですね」
「では、道中お気をつけて神のご加護がありますように」
「そちらこそ」
彼女は笑って別の道へ行った。
予定より早く着いてしまったので住民の喫茶店に入って休憩することにした。ハーブティを頼んで腰を下ろす。
「はい、どうぞ」
店のおねえさんは笑って、
「この街には砂を買いにきたのかい」
「この街にあるのは砂だけじゃありませんよ。私は砂を買いにきましたがね」
「ふふ、ここに来る人はみんなそう言うんだよ。今日は建国一周年だよ、ゆっくりしていきなね」
「ありがとうございます」
お言葉に甘えて予定より長く居座った。店に帰るのが遅くなるかもしれないが気にすることはない。店主は店に帰ってくるまでに到着していれば問題はないのだから。
窓から外を眺めていると遠くで大きな光が見えた。目を細める暇もなく次に爆発音が轟、同時に俺は店内の壁に叩きつけられた。なんとか起き上がって割れた窓から外見ると光は大きくなっていきこちらへ迫ってくる。店の外を歩いていたであろう住民や妖精は何事かもわからず爆風で倒れこんでいる。光の方向をよく見れば大地が捲れて宙に吹き飛んでいくのが見える。他の住民もそれに気づいたようで動けるものは逃げ出していた。俺もそれに倣い走り出そうしたが店内からおねえさんのうめき声が聞こえた。厨房で横になっていた。おねえさんを抱きかかえて店から走りだそうとするも光はもうすぐそこまで来ている。
視界には親子が抱きしめ合っていて逃げることを諦めているのが見えた。他の住民も同じようにしていて俺も彼女を抱きかかえたままどうすることもできないことを悟り座り込む。大地はゴゴゴと揺れ始めやがて轟音とともに光は迫ってきてやがて皆飲み込まれた。
目覚めると白いオフトゥンで横になっていた。
「お、お前、か、体に痛みはないのか」
声をかけたのは店主だった。
「いや・・・ないですね。ここは・・・」
「王立病院だ。何があったかわかるか」
店主は切羽詰まっているようだった。
最後の光景を思い出して、
「光が・・・」
「・・・バトル街に雪が積もっている」
「は」
意味がわからない。バトル街に雪が降るような地形が生まれるはずがない。
「ど、どうして」
「魔王だ。王国は魔王の出現を許したらしい」
魔王など伝説のものに過ぎないのではなかったのか。
「バトル街はいまその現象に歓喜して地形開拓を始めているぞ。流通が大きく変わるに違いない・・・だが、多くの者が傷ついた。今ここの病院もけが人であふれているところだ」
店主は怪訝そうな顔をして、
「なあ、それなのにどうしてお前には傷ひとつないんだ?」
その日は仕事を休み、翌日から仕事へ逃げるように店主の依頼を了承した。
今日はパール街まで買い物だ。いつもは気乗りしない買い物も今は暗い気分から抜け出すことできる唯一のものに感じる。
店を出るとブルー街の住民たちは祭り騒ぎとなっていて人でごった返していた。空へ飛ぼうとしたとき別の妖精と肩をぶつけてしまった。
「すみません」
その妖精からは返事はなく不愛想なやつもいるものだと再び飛翔した。街を抜けて木の横をかすめながら買い物リストを確認しようと胸ポケットに指を入れると身に覚えのない紙があることに気が付いた。
木の枝に座ってその紙を確認する。簡素な名刺で店名とエメラルド街の住所が書いてあった。
「本屋が何の用なんだ」
最近、独り言は増えてきた。
パール街の帰りにエメラルド街へ寄って名刺をくれた本屋をこの目で確認することにした。そこは道から外れて草原の真ん中にあった。さすがの大都会エメラルドと言えど道から外れると人は少なく妖精一人がここを飛んでいると目立ってしまう。
「そこの旅のお方、お待ちしていましたよ!」
下から男の妖精の声が聞こえた。呼びかけに応じて店の前に降りる。
「ずいぶん粋な広告を寄越されますね」
方眉をあげて陽気に、
「はは、広告ではありません。それは招待状ですよ」
「店主と商談かなにかでしょうか」
「それなら直接店主に紹介状を送りますよ。ここではなんですから中に入られませんか?」
店内に入ると絵本が並べられていて本当に本屋らしい
男は両手を広げて、
「ようこそ老舗の本屋へ。ふふ」
「そんな本屋がどういったご用か検討もつきませんね」
机の前に座るように促されてお互い向き合うように座る。
「私は英雄譚が好きなのですよ。本に描かれる英雄というのに私は心惹かれます」
「あなた自身が勇者になられないのですか?」
男は俺から視線を外して上を見つめ、
「生憎、私は体が弱くてね、勇者は叶わなかったよ」
「申し訳のないことを訊いてしまいました。すみません」
男は笑って視線を戻し、
「はは、いえいえ、作家も気に入っているのですよ。夢のような話を書けておかげで子供たちからは人気なのですよ。子供たちに直接売っているわけではありませんが彼らの笑顔が見ることができるので嫌いではありませんな」
「本題が読めませんね」
「あなたは運び屋に満足されていますかな」
「これが俺の仕事なんでね」
「あなたの目からは何も満足感が感じない」
心を見透かされているようで良い気がしない。
「さあ、毎日遠方に品物を買いに行かされて疲れているだけじゃないですかね」
「ふふ、それもあるのでしょう」
男は視線を店の外に向けて会話を続ける。
「バトル街に続きエメラルド街、アダマンチウム街でも同様の大規模な爆発があったそうですよ。エメラルド街では溶岩が噴出して大惨事となりすぐに開拓し直されましたが、アダマンチウム街では熱帯季節林が生まれて受け入れられたようで拡大開拓が進んでいるようで」
「うちの店主も物流が変わるだとか言って冷や汗を流してますね」
「はは、街の特性が変わるのだから大きなことですね」
「まるで他人事のようですね」
「・・・それは屋内で仕事をする作家からすれば全くの他人事ですよ、ふふ。そのどれらも多くのけが人が出ました。」
男は再び俺に視線を戻して、
「あなたを除けばね」
「・・・運が良かったんですよ」
「噂になっていますよ。爆発のど真ん中にいたのに傷ひとつなかったとね。で、その有名人の顔を拝むために今日は招待したわけです」
「どうやら、願わない形で有名人となったようです」
「それほどの強靭な体を持ちながらどうして勇者にならないのかな」
答えない。
「予定の輸送時間から遅れているので俺はここで」
「今度、あなたの旅に同行してもよろしいですかな」
「・・・ええ、構いませんよ。ちょうど一人でいるのに飽きていましたから」
男は笑いをもらした。
それから数日が経ったが男の姿は見ていない。今日は久しぶりのバトル街への買い物となっている。店主が気を利かしたのかどうか知らないがしばらくバトル街へ行く仕事はもらわなかった。今日、店を出るとき店主は「ついでにバトル街の雪でも見てきな。帰りは時間厳守だがな」と言っていた。時間は一度も守ったことがないが気づかれていない。
店を出ると作家の男が立っていた。
男は如何にも営業用の笑いを浮かべ、
「今日はどちらまで?」
こちらは販売や商談に応じるわけではないのだから笑顔では応じない。
「バトルです」
「おお、それはいいですね。私もバトル街の開拓の進捗をこの目で見たかったのです」
作家が旅をするとは似合わないものだ。
「良いんですか、お仕事をせず遠出をして」
「ふふ、屋内で壁ばかりを見つめても良い物語というのはできないものなのです。よくこうして 街の外まで飛んでは話を考えていたりしますね」
「そういうものですか。お身体には障らんのですか」
「空を飛ぶくらいなら問題ありませんよ」
「では速度を上げてもいいですかね」
男はこれには困り顔で笑い「はは、輸送特化店舗の加護を受けた妖精の最高速には追い付けませんよ。ところでバトル街では何を買いに?」
「砂・・・、とは言えなくなったんですね。今日は氷です」
作家の男はその後、一人で自身の書いた物語の内容を喋り続け、俺はただ相槌をしているだけで彼は満足しているようだ。物語のどれも興味魅かれるものだった。そろそろバトル街も見えてくるようになった頃だ。
「実は、うちには店主がいないのですよ」
「いない?」
「というよりも“いた”のですがいつごろか店には来なくなりました。気まぐれ妖精にでもなることはできたのですが何もしないというのはさすがに面白くはないので私が切り盛りしているところなのです」
「随分とまた不思議な店ですね」
「仲間の何人かは立ち去ったのもあって不完全な店ではあるのでそれも不思議な店といえるでしょう」
男は間をあけて言葉を選ぶように、
「そして私はあなたも不思議な存在に見えている」
「傷がなかったことにそんなに興味を持たれますか」
「はい、バトル街、アダマンチウム街、エメラルド街とどれらも爆発現場にいた誰もが負傷しているのにあなたは例外だった。それと同じくらいなぜあなたが勇者をなされていないかも不思議に考えています」
男は試すような目で見てきた。それに俺はため息を吐くことで応じ、
「昔はしていましたよ。もうやる気はありませんがね」
「店主の方針変更ですかな?」
「いや、勇者をしていたのは前の店主のときでした。もうその店はありませんがね」
「そのときのあなたは仕事に満足されていたはずだ」
また、男は見透かしているような目で見てくる。
「・・・ふ、どうだか。・・・去年の夏に出現したヴァンパイアのことは覚えられていますか」
男は記憶を掘り出すかのように顔をしかめる。
「ええ、たしか・・・追い払うために勇者の装備を用意するのに当時苦労されたと聞いています」
「そうです、何が有効であるかわかりませんでしたから。対ヴァンパイア装備一式を開発するまでは多くの勇者が傷つきました。その一人に先輩勇者がいましてね。当時は名をはせた勇者でしたが装備も整えることできずあえなく返り討ちにあいました。その後先輩は勇者を続けることが困難になり引退したわけです」
「それはお気の毒です。しかし、その後原初のヴァンパイアは討伐されませんでしたか」
「・・・それを討伐したのが俺です。勇者を引退せざるを得なくなった先輩は殺されたも同然と俺は感じたのもありかたき討ちができたと俺は思いましたよ。ただ、そばにいた妖精だかヴァンパイアだかわかりませんが彼女の顔が忘れられんのです。彼女は一言、許さないと言ってその場から立ち去りその後追っていません」
「今ではヴァンパイアも数を増やして一つの勢力にまで成長しているようですな」
「・・・彼女はその後気まぐれ妖精たちをヴァンパイアにしていったとまでは聞いていますが俺にはもう十分でした。先輩は勇者を引退し何よりも彼女のあの涙が堪えました。勇者を続けることはできませんでした」
情けなく感じて、「ふふ、絵本のネタとしてどうです?」
「とてもこんな悲劇的な話に子供は喜ぶとは思えませんな」
男は口の端を吊り上げて続ける。
「ただ、まだそれがエンディングと決まったわけではないでしょう」
「終わりですよ。英雄譚からはあまりほど遠い」
「いいや、終わっていません」
男の語気は強くなっていく。
まるで台本でも読むかのように、
「再度問いましょう、あなたは今の仕事に満足されていますか?」
勇者をしていたときはいつも毎日が気持ちよく満足できていた。ただ今勇者に戻ったところで満足感を得ることができるだろうか。できないかもしれないことが恐ろしい。できないと知るくらいなら過去の良き思い出として綺麗なままにしておきたい。
「・・・時間をください」
「ふふ、急ぐことはありません。もし勇者に戻られるのなら装備はこちらが用意しておきましょう」
「全部用意するには高いだろう」
「お金を貯めたって仕方ありませんし、何より物語のネタとして英雄の復活を描けるのだとしたら安いものです」
悔しいが笑わされてしまった。「はは、それはあまりにも出来すぎている」
バトル街に着いて砂漠の隣に広がる雪原に入った。以前バトル街に来たときとは比べ物にならず バトル街にいるとはどうしても思えなかった。
男は独り言のように呟く。「・・・前より雪原が広がっている」
「一度見に来られましたか」
「ああ・・・、ふふ、そうです。作家なら物語を生むためにもこんな現象が起きたらこの目で見ずにはいられません」
「真面目ですねえ」
「申し訳ない、物語のネタを思いついてしまった。ここで失礼するとします」
「良い物語ができるといいですね」
「ふふ、それは半分あなたに懸っていますよ。いつでもうちの店へどうぞ。お待ちしております。ではでは」
読めないお人だ。
翌朝、輸送の仕事を店主から命令される前に店を出る。意思は固めていた。最高速度でエメラルド街へ行き本屋の前に降りると男は両手を広げて待っていた。
息を整えて、
「何をすればいい?」
「来られると信じていましたよ。ふふ、中へお入りください」
部屋を用意されていて中に入るとミスリル製装備一式と食料、薬品などが置いてあった。
男は精錬された笑顔で、
「ふふ、スライムを相手にしてもらっても構わなかったのですが伝説の勇者様には失礼にあたるだろうと思いましてね、近くの住民がドラゴンに悩まされているようです。助けにいかれてはいかがですかな?」
男は試すような目で見てきた。
久しぶりに防具を身に着けた。ようやくドラゴンの仕事を引き受けられるようになった頃のことだ。初めてのミスリル製の防具を装着して舞い上がっていたところを先輩に「ミスリル製の武具は君には似合わんね」と言われて落ち込んだことを思い出して笑いをもらす。今となっては悪くない思い出だ。
「ううむ、勇者なのにミスリル製装備一式は似合いませんな?」
「はは、あなたまで言いますか」
男は困った表情を見せて、はて?と言い、
「私の新作の物語もあと少しで終わるところですよ。物語の制作にぜひご協力ください、ふふ」
「そいつは出来が楽しみです」
「・・・今回は自信作となっていますよ。では、お気をつけて」
「久しぶりだなあ、ドラゴンさん」
緊張感から生まれる高揚感、思わず口の端をあげていた。
ドラゴンの咆哮、横なぎに来るかぎ爪を剣でいなす。
「はは」
心の暗さはすべて吹き飛び喜びだけが満たされていった。
「さあ、ここからが長いぞ」
大量の魔石とドラゴンが残した秘宝の在処を記した地図を男の本屋まで持ち帰る。
「いいですね、その目、満足感に満ちている」
そう言われて悪い気はしなかった。
「ありがとうございます。あなたのおかげです。この魔石と宝の地図です。これで装備費を補てんしてください」
「ふふ、では遠慮なくそうさせて頂きます。いえいえ、こちらこそ。おかげで新作が出来上がりました。ふふ、今度発表会を催すのですが来ていただけますかな」
「もちろんです」
「今後の勇者活動はどうされるのでしょう」
「さあ、うちの店主はよしと言ってくれなさそうですから他の店に行く必要がありそうですね」
「そうだろうと思いましたよ。よければうちでされませんかな」
「はは、断る理由はありませんね」
「ふふ、新作発表会については追って連絡します。今日はお疲れでしょう、ゆっくりお休みください」
男二人で気が済むまで笑ってからその場を後にした。
男の新作発表会は三日後と連絡が入りそれまで運び屋の仕事をすることで先日の非礼を詫びるとともに店主とも合意した。「やっぱり、お前には運び屋は似合っていないと思っていたんだよ」とも言われた。
三日後、契約を終了させ男の本屋へ向かう。輸送特化の加護はなくなり普通の速度でエメラルドに向かい普段より街が遠く感じた。
本屋に着くといつもの閑散とした本屋ではなかった。男は来場者に感謝を述べていたところで俺の姿を見つけるとキリ良く祝辞を終わらせた。
「やあ、よく来てくれた」
右手を差し出され握手する。感謝の念は尽きない。
「盛況のようですね」
「ヒット間違いなしですな」
男は手を店の奥へ向ける。どうやら彼の部屋らしい。男に案内されながら部屋に進む。
「ホントに感謝してもしきれません」
「なんのなんの、あなたが勇者になってくれて私もうれしく思います。これで登場人物はそろいましたな」
男からいつも笑顔が消える。
「・・・俺だけではない?」
男の部屋は広く、見ると壁には剣が並べてあった。
「ど、どうしてエクスカリバーが・・・」
「私は英雄譚に描かれるような勇者になりたかった・・・。しかし、この体はそれを許してくれなかった」
よく見ると計画書のような紙も壁に付けられている。バトル街の地図とある地点に大きくバツ印、エメラルド街、アダマンチウム街にも同様であった。
それはまるで自分の存在を明らかにするように。
「・・・な、何の話をしているんだ・・・」
「私は勇者にはなれなかったのだがね、私の配役は別にあったのだ」
俺は混乱して答えずにいるところを男は低い声で続ける。
「私は探したのだよ、勇者にもなれず体の弱い私の真反対の存在をね。そしたらいたのだよ、君がね。あれほどのことがあっても無傷でいる君が」
「・・・お前がやったのか・・・あれを・・・」
男にいつもの笑顔はない。
「情報が入るのが遅くてね。エメラルドとアダマンチウムでもやってしまったよ」
「どれだけの人が傷づいたかわかっているのか」俺の声は震えている。これは悪い冗談ではないのか。
男は目が全く笑っていない笑顔を浮かべ、
「くふふ、それが魔王の仕事だろう?」
「狂ってる」
怒りに任せて男に殴りかかるが直前で壁を殴ったかのように拳は止まる。
「くふふふ、無駄ですよ。それは素手で破れるようなものではない」
俺はその場か逃げるように歩き去る。
「これが俺の配役だったんだ!仕方がないだろう?!」
返事はしない。「・・・くそ」
その後男は姿を消した。エクスカリバーを使用する際に大地を破壊する際に生まれる被害を最小限に抑えるために事前に住民が避難することで対策された。エクスカリバーの運用にはいまだ賛否両論ある。

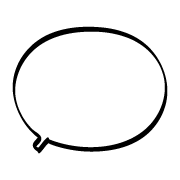



 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です