月が照らす洞窟から化け物が出てくる、周囲を紅色の光沢に染めながら。
妖精は夢を見る。彼女の場合は過去の記憶を再生していた。店主と共に様々な街を旅し、テントを張っては商売に明け暮れ、雨の日も気にせず笑いあった日々が流れていく。その店主はもういないことを思い出して、彼女は目覚める。店主の顔はもう思い出せない。
気が付けば樹穴で横になっていた。立ち上がり穴から目を細めながら外を見れば、太陽はすでに真上まで昇っていた。昨晩は夜遅くまで仲間達と飲んでいたものだからかもうこんな時間だ。樹穴から飛び立ち後ろを振り返って彼女がお世話になった木に礼をする。その木を選んだのは彼女の気まぐれだった。
それからしばらく森の鳥たちと遊び、疲れた彼女は小枝に座って一息つくことにした。下から声が聞こえる。
「朝の運動を終えたって顔しているね」と得意そうに言うのは、ここをよく通っては彼女に声かけてくる荷物を運んでいる妖精の彼だった。
「どんな顔よ。それに、もう朝なんかじゃないでしょう」
「どうせまた日が出る頃まで飲んでいたんだろう?」妖精は笑う。
「日が出るころだったかどうかは覚えてないわ」昨晩の自身の行動を振り返りながら苦い顔をする。
「はは、ほんとお酒が好きだねえ。どうだい、うちの店でお酒を造らないかい?うちの店主も喜んでくれると思うんだ」
彼女は間をおいて、
「…気が向けばね。それに私は飲むのは好きだけど造るのは得意じゃないの」
「そりゃあ残念だ。これ以上君の邪魔をするはよくないだろうからね、ここで失礼するよ。またね」
彼女の邪魔というよりかは彼が時間に追われている様子だった。
「うん、またね」ひらひらと手を振って彼を見送ってから空へ飛んだ。
森で一番背の高い木頭に座って青空の下、気持ちのいい風に当てられ店主のことを思い出す。先ほど誘われたためにもう一度店主と共に働きたい気持ちが湧き出る。だがあの店主以外の人とは働きたくはなし旅もしたくはなかった。何も考えないようするためにぼうっとする。
しばらくして、森の端にある街から紅色の光が目に入る。それに惹かれた彼女は街へ向かう。それも気まぐれで、気まぐれでいるほうが楽だった。
街に降りると人々の悲鳴でいっぱいだった。逃げ惑う妖精に聞くところによれば街に化け物が現れて街を血に染めているのだという。そんな化け物を聞いたことがなかった彼女はその正体を一目見るべく人々が行く反対に向かって飛んでいくことにした。
街に似合わない静かさに満たされ、若干の緊張を覚えた彼女は家々に隠れながら進み、紅色の光沢に染められた広場に出る。その光景に息を飲んだ。この世の物とは思えないくらい綺麗だった。しばらくその街並みを呆然としていると街角から人影が現れた。慌ててその人の下へ飛ぶ。
彼は虚ろな表情でいて、彼女の存在に気づいていないようだ。
心配になった彼女は「大丈夫?」と肩を軽く叩きながら問いかけた。
そこでやっと彼は彼女に気が付いてようで二呼吸ほど目が合わせていた。すると彼は涙を流し始めた。
「怪我しているの?何があったの?」
怪我をしていてはいけない。彼女は彼の周りを飛び回って怪我がないかどうかを調べたが運が良かったようで見た限りでは怪我はしていない。
彼は嗚咽交じりに何かを言ったが彼女には聞き取れなかった。
「どうしたの?」
「ああ…」彼は辛そうな顔を浮かべた。
「はっきりして」彼女は心配から催促した。
「これをやったのは…俺のようだ」声が掠れている。
「これって?」
錯乱しているのか。
「ま、街をこんなのにしたのは俺なんだ」声が震えている。
「ええ、でもみんなは化け物がなんだのって…」
「…俺がその化け物だ」
「よくわからないけど、私にはあなたが人に見えるわ。ここにいたら危ないから街から出ましょう」
そう言って彼女は彼の手を引っ張った。
なるほど、どうやら彼の言っていることは正しいようで街を出てからというもの草原が広がっていた場所は彼を中心に紅色の光沢に覆われていく。どこからともなくごつごつとした紅色をした石に変わっていく様は不思議な光景だった。彼女たちが通った草原は街の大通りほどの大きさに紅色に染められる。
彼が俯きながら歩いていたものだから、「前を向いて歩きなよ」
「こんなに綺麗な景色を汚くして行く光景を見たくない」
彼の顔色が悪い。少し先の丸い岩を指さして、「あそこに座りましょ」
彼は苦笑して「ああ、ありがとう」
岩に腰を下ろすころには岩は紅色になっていた。
なおも俯く彼に苛立った彼女は「いつまでもそうしていちゃいけないよ」
「最初から綺麗な景色を見なければ俺がどれだけのことをしたのか知らなくて済むだろう?」
「そう?どうして汚いと思うの?私は綺麗だと思うわ、その、赤いの?ていうか何なんだろうこれは。私からすれば飽きるほど見た景色が別の綺麗な景色になっていくだけよ」
彼女は恐る恐る草の形をした紅色の石を手で触れると草の形が崩れていった。
「綺麗、だというのか?これが、あそこにいた者は嘆いてたじゃないか」彼は苦しげな表をする。
「それにこれがあなたの行いによるものなのだとしたら、しっかり胸を張って向き合うべきだと思う」
間をあけてから「胸は張れんだろうが向き合う必要はあるだろうなあ」と言う。
決心がついたように、ようやく彼は顔を上げる。
「それに、すべてを変えられるわけじゃないでしょう。空とかね」
「それとどうやら君もね」彼女たちは青空へ仰ぎ笑っていた。
しばらくして、歩くことを再開した彼女たちは彼が街へ向かう時にできた紅色の道を辿って彼がもといた場所へ向かうことにした。彼が言うには記憶がないらしく目覚めたときは山の洞窟だったそうだ。
彼の道は草原の広がる山に伸びており彼の目覚めたという洞窟へ途切れることなく続いていた。
「それで、ここがあなたの目が覚めたところってわけね」
「日が昇る前に目覚めたことを記憶している。周りが明るくなってから山を下りようとしていてうろうろしていたためかご覧の有り様だ」
洞窟から一帯は紅色に染まり夕日の光も混ざってその光景には息を飲むものがあった。
「そのようね。…本当に綺麗だわ」
「そこまで言われるとなんだか照れるな」彼は苦笑する。
「ふふ、向き合えてる証拠ね。洞窟を見てみましょう」
洞窟は人一人の部屋ほどの大きさのみでどこかへ続いているわけではなかった。
「まるで、あなたのために用意された部屋ね」
「用意されたというならベッドの一つは置いてくれもいいと思うがな」
「ベッドで寝た、という記憶はあるの?」
彼は片手で顎をさすって思案した様子を見せる。
「いや、寝るときにあると最高に心地の良いということしか知らないな」
「そう、何かの手がかりになれば、と思ったのだけれど」
「すまないな」
「こちらこそ力になれそうになくてごめんね。それより空腹感や喉の渇きは感じていない?」後半は気づかず早口に。
「いやあ、特にないな。あったところで食べるころには石になっているのだろうから食えそうにないだろう」
彼女はなにか悪い予想がよぎったがあえてそのことは言わずにおいた。
「なら、あなたとの食事は楽しめそうにないわね」
「はは、そりゃまた残念なことだ」本当に惜しいものだという顔をして彼は笑う。
彼女は視線を彼から沈んでいく太陽に目を背けて「日も暮れてきたから私は帰るとするわ。あなたに名前はあるの?」
しばらく唸ってから自信なさげに彼は答えた。「ヴァン…パイア、ヴァンパイアだったかな」
「ヴァンパイアねえ、呼びづらいからヴァンでいいかしら」
「おお、ありがとう。そっちのがいいな。君の名前を聞いても?」
「カーミラよ。今日はありがとう、楽しかったわ」
「カミーラか、いい名前だね。こちらこそありがとう、一人ではとても心細かったんだ。今日は助けてくれて、本当に」彼は彼女の手をやさしく両手で添えて「本当にありがとう」
「そこまで感謝しなくていいわよ、私の気まぐれなんだから。また明日の朝来ることにするわ」
彼の両手は暖かった。
翌朝、カーミラが洞窟まで飛んでいくと女性と思われる悲鳴が聞こえた。岩陰に隠れて様子を窺がう。どうやらオリハルコンの武具に身を包んだ複数の勇者が彼に挑みかかっているようだ。防具はヴァンの傍にいるだけで緩やかに紅色に変色していっている。状況は彼の方が優勢に見える。彼は片手に紅色の棒状の物を持っては斬り込んでくる勇者たちをいなしている。もう片方の手を広げて勇者に向ければ防具が紅色に染まっていくのが加速する。それは身体にまで及んでいるのだろうか。4人の勇者達は為すすべなく撤退していく。ヴァンは彼らに追い打ちはしかけるつもりはいないようだ。
カーミラは急いで彼の下へ飛ぶ。
「怪我はない?」
突然背後から彼女に声をかけられた彼は驚いた様子で思わず声を上げた。
「驚かさないでくれ、心臓に悪い。ああ、怪我はない」彼は笑顔を見せる。
振り返った彼の両の目の虹彩は赤色に明滅していた。
「よかった。あの妖精たちとは何があったの?」ほっ、と息をつく
「昨日、俺が街に降りただろう。その時に何人もの住民が重傷を負ったそうで王国は俺を危険性のあるものと決定したそうだ。」
「ああ…」彼女の悪い予想は当たってしまったために思わず声を出してしまう。
彼は彼女の様子を見て不安げに「街に危害を加えた俺を、君はいいのか?」
「あいや、ごめんなさい。予想はしていたの。ただ、それをヴァンに言えなくて。街の妖精じゃない私は特になにか思うことはないわ、安心して」正直でいなかったことの申し訳なさもあって笑いかける。
「カーミラの仲間であることに違いはなさそうだが…、これで人里にはいけないなあ」
「あなたを敵視するようなところへなんか行く必要はないわ。それにここから見える景色はいいものじゃない」景色に目を向ければ広大な平野がずっと向こうの山まで続いて、広い森や街に川が並んでいる。
「ただ、ずっとここにいることは無理そうだな」
「どうして?」
「勇者が追ってくるだろう、どちらにしたって足跡を残してしまうから追われそうなもんだが」
「ならいろんなところに足跡を残したらどこへ行ったかわからなくなるんじゃない?」
「そりゃあ良い、できるだけ人のいないところ、この山の裏側とかいいんじゃないか」
「そうと決まれば早速行きましょう」
それは二人の軽い散歩だった。
それから数日が経ち、カモフラージュのためにいろいろなところへ足を運んだ。街から見て山の裏は山々に囲われていた。すでに緑はほとんどなく紅色に染まっている。
それでも勇者達は執拗に追いかけてきて見つけてくる。その度に返り討ちにされたが数で押してきて彼も危ういときが何度もあった。
今も10人を超える勇者が挑んできてヴァンが負傷することも増えてきている。カーミラは何もできないことがむず痒くて仕方なかった。
今回もなんとか退けたが傷が深く急いで手当に移った。
その夜、カーミラは正直に告げた。
「ずっとこのままじゃヴァンの身体がもたないわ。何かいい案はないかしら」言うも答えは出ている。何もできない。
「どうしたものかなあ」彼は顎を手でさする。
「心配で仕方ないのに何もできない私が許せないわ」
「何もなんていうことはないだろう?怪我の手当だってしてくれているじゃないか」
傷を見ればすでに治りかけている。彼女の手当によるのもあるのだろうが彼自身の治癒力も高いからだった。
しばらく彼がうなってから切り出した。
「仲間は増やせられるようなんだ」バツが悪そうに彼は言う。
「仲間?」きょとんとする。なら前から増やせばよかったのではないか
「その…、なんと言えばいいか。人なんかを俺と同族にすることができる、ようなんだがしたことがないんで実際のところ、俺もわからん」
「私もなれるの?あなたみたいに」
「…、おそらくは」気恥ずかしそうだった。
「ならお願い、私をあなたと同じようにして」助けられるかもしれない。
「いいのか?戻れはしないはずだ」
「かまわないわ、それに妖精でいるのも飽きたもの」
「しかしなあ…」言ったことを半分後悔している様子だ。
「いいから、早くして私の気まぐれが変わらないうちに。どうやるの?噛んだりするの?」少し恐さもある。
「いや、噛んだりはしないさ」彼女の手を取りやさしく引き寄せ「こうやるんだ」
彼は彼女に唇を合わせた。
彼女は目の虹彩を赤く明滅させ血の涙を流して笑っていた。
彼女はそれは気まぐれだと自身に言い聞かせた。

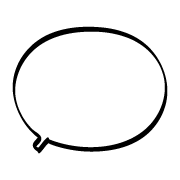

 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です