「店主さーん。私たまにはハーブティーじゃなくて別のものがほしいし、最近寒いわー」
作業室にアリーの高い声が響く、砥石でインゴットを磨く音や紙の上をペンが滑る音が跋扈している中でもその声はよく通り、本や紙束、インゴットにませきと倉庫から取り出され、作業の為に雑多に並べられたそれを振動させる。
「あのな、アリー。悪いんだが今うちは……」
アリーからの本日3度目になる要望に店主は苦虫をかみつぶしたような表情で応える。今輸送妖精たちは皆仕入れの為に出払ってしまっており、とても妖精たちへの労いが出来る状態ではないのだ。
「まあたそれ?いつになったらそれは終わるのよー」
ここ暫く、店主は「ガクフ」というアイテムの市場をどうにか是正したい。などと言って店の経営も怪しくさせつつ営業を続けている。そのアイテムを買い上げるためにも資金が必要で結果として訪れているのがこの作業・輸送・販売・倉庫に加えて店主までもがロクに休みもなく働いている状態だ。流石に店主も疲れが溜まっているのか顔に疲労の色が色濃く出ている。
「悪い……」
「仕方ないわね。じゃあそれが終わったら私達にもぼーなすっての頂ける?」
萎んだ顔で済まなさそうにする店主にやれやれとした仕草で応じるアリー。内実アリーはこのやりとりをするのが愉快でならなかった。アリーはこの店開店からのスタッフでこの男の成長をよく見ている。当初、何もわからないままAと名乗る農家にこの島に連れてこられた男、何の変哲もない質素な服だけでほっぽり出されたこの男が店を出すのだと言って政府に来た時、派遣されたのがアリーだった。
この店最初のお客さんはお坊ちゃんだった。確かお母さんにお使いを頼まれて薬草を買いに来たのであったか。あの時丁度書きあがった近所の地図も一緒に買っていってもらった記憶がある。
あの時は二人して地図の書き方も何もわからず水から紙を漉き、色草をつぶして作った顔料を鳥の羽を使ってペンにした。ひたすらな苦労をしてやっと書き上げた地図を買ってもらえた時、店主と二人手を叩いて喜んだものだ。
それが今となってはいつも市場の値を見て眉間に皺をよせるようになった。身なりはあの時から悪化し、ぼろぼろな質素な服になっているが顔は随分精悍になった。
ここの住民は短命で、わずかな間で一生を終える者もいる。今まで何人ものお客さんが亡くなったとの話も聞いた。その度に何度も涙を流すこの男をアリーは親しく感じている。ジキュウだのリエキリツだの最近難しい言葉も言うようになってきたがこの男の本質は変わらない。いや変わらずにいてほしいと思う。特にこの男をからかったときに見れる困った顔なんてのは特に傑作だし、何よりお客さんが喜んで商品を買っていった時笑う男の表情がアリーは好きだ。
「あ、そうだアリー。確か保管庫にこの前貰った蜜柑があっただろう」
以前新入りのシルヴィエといった作業妖精が書いた申請書を使ってピクニックに行ったのだ。確かその時農家さんに蜜柑をもらった。確かそのまま捨てるのも悪いからと保管庫に入れておいたのだ。
「ああそういえばそんなのもあったわね」
「確か端数だったろう。保管庫にビンもいくらかあったはずだ。一緒にもっていってポンジュースにでもするといい」
いつか見た優しい顔で男は言う。この男はこんなところがズルいのだ。他の店主でこんな奴はきっといないとアリーは思う。妖精達と一緒に泣き、笑い。一緒にいて楽しいと思える店主は大切にしろとよくいう。妖精達はあくまで仕事にすぎず、ある程度の成果を出せばそれ以上の努力は必要とされていないからだ。
「もう、仕方ないわねえ。淹れてくるからちょっとまってて」
随分精悍になった顔に昔の色を思い出し、アリーは美味しいポンジュースを淹れてやろうと保管庫に向かう。できる限り多く作って他の妖精達にも配ってやろう。
「あ、おいアリー?仕方ないなあ。」
あの様子だと自分にも淹れるつもりだろう。最近頑張らせっぱなしの妖精たちには嫌われていないか不安にばかり思っていたのでどうにも大丈夫そうだと思った店主は微笑みを零し近くに詰まれた楽譜を持ち、この寒いままでは悪いだろうと暖炉に近づくのであった。
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
先輩妖精アリーのお話
関連投稿
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 【2022年7月版】住民財布額からみた住民売り利益期待値早見表haguruma / 4435 view
【2022年7月版】住民財布額からみた住民売り利益期待値早見表haguruma / 4435 view -
 住民売り考察日記㉖住民コメント・購入失敗確率haguruma / 4080 view
住民売り考察日記㉖住民コメント・購入失敗確率haguruma / 4080 view -
 住民売り考察日記⑯業種レベル考察haguruma / 2592 view
住民売り考察日記⑯業種レベル考察haguruma / 2592 view -
 住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3084 view
住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3084 view -
 イメージ画像を描きたい人への何かの支援になればおさかな#38412 / 3834 view
イメージ画像を描きたい人への何かの支援になればおさかな#38412 / 3834 view -
 卸売りの値付けトロピ / 4618 view
卸売りの値付けトロピ / 4618 view -
 木刀チャレンジをしてる話猫の店 / 3524 view
木刀チャレンジをしてる話猫の店 / 3524 view -
 水と氷はどこから来るの?そらまん / 8168 view / 3
水と氷はどこから来るの?そらまん / 8168 view / 3 -
 Yossi放浪記(Md記法練習編)yossi8382 / 3823 view
Yossi放浪記(Md記法練習編)yossi8382 / 3823 view -
 作業選択の基準(しょしんしゃ向け)千春 / 8078 view / 2
作業選択の基準(しょしんしゃ向け)千春 / 8078 view / 2
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 【2022年7月版】住民財布額からみた住民売り利益期待値早見表haguruma / 4435 view
【2022年7月版】住民財布額からみた住民売り利益期待値早見表haguruma / 4435 view -
 住民売り考察日記㉖住民コメント・購入失敗確率haguruma / 4080 view
住民売り考察日記㉖住民コメント・購入失敗確率haguruma / 4080 view -
 住民売り考察日記⑯業種レベル考察haguruma / 2592 view
住民売り考察日記⑯業種レベル考察haguruma / 2592 view -
 住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3084 view
住民売り考察日記⑨他店のバフhaguruma / 3084 view -
 イメージ画像を描きたい人への何かの支援になればおさかな#38412 / 3834 view
イメージ画像を描きたい人への何かの支援になればおさかな#38412 / 3834 view -
 卸売りの値付けトロピ / 4618 view
卸売りの値付けトロピ / 4618 view -
 木刀チャレンジをしてる話猫の店 / 3524 view
木刀チャレンジをしてる話猫の店 / 3524 view -
 水と氷はどこから来るの?そらまん / 8168 view / 3
水と氷はどこから来るの?そらまん / 8168 view / 3 -
 Yossi放浪記(Md記法練習編)yossi8382 / 3823 view
Yossi放浪記(Md記法練習編)yossi8382 / 3823 view -
 作業選択の基準(しょしんしゃ向け)千春 / 8078 view / 2
作業選択の基準(しょしんしゃ向け)千春 / 8078 view / 2

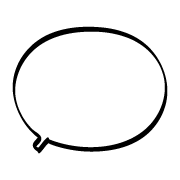


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です