――ねぇおじちゃま、これはなぁに?――
ある晴れた日のことだ。まぁるい目をした実に可愛らしいおじょうさんが、私の露天をのぞきこみながら尋ねてきた。釣り具、魚、塩、水、古びた宝箱……雑多なものであふれかえる、その片隅に置いたビン。おじょうさんは、それが気になるらしい。
――お目が高い。これは知るひとぞ知る秘密の飲み物だよ。ただね、大人しか飲むことができないんだ――
きみにはまだ早いかな……そう言うと、おじょうさんは残念そうに肩を落とした。
――なぁんだ、そうなの。ガッカリ。……ねぇおじちゃま、これはなんなの?――
それでも、好奇心は消えはしなかったようだ。茶色い水の入ったビンにそっと触れる。
――気になる? ……そう、なら、おじょうさんだけに、この飲み物の秘密、教えてあげよう……――
おじょうさんの指先で、細長い影がひっそりと揺れた。
***
彼らはこの水に浸かるのが大好きなんだ。昼に飲むと何故か怒られる、この水のことを知ってるかい? ……そう、魂の水だよ。私は彼らをこの水に浸けてあげる秘密のお仕事をしている。当局にバレると叱られてしまうから、こっそりとね。
何故叱られるかって? それはね……彼らが魂の水を大好きすぎるから。放っておけばいつまでだって、このビンの中で飲み続けている。そうして気付いた時にはとろりとろりと溶けていって、一回りも二回りも小さくなってしまうんだ。
――彼らの体が溶けているから、この水は濁って茶色くなってしまうのさ……。
***
私の話を聞き終えたおじょうさんは、触っていたビンからそっと手を離した。
――そのうちぜんぶとけちゃうの?――
私はそのビンを持ち上げて、ちゃぷんと水面を揺らす。ずいぶん小さくなってしまったけれど、まだ十分姿は残っている。
――全部溶ける前に、私の方がおじいちゃんになってしまうよ。彼らはとても長生きで、丈夫なんだ……――
そしてとても美味しいんだよ、と私は付け足した。
――この飲み物はね、とても、とても美味しいんだ。一度口にしたら夢中になって、夢に見るくらいに、ね――
……好奇心に果てはない。それはまだ幼いおじょうさんであっても。私の顔と濁ったビンを交互に見比べるおじょうさんに、私は未来への布石を打った。
――大人になったら、またおいで――
おじょうさんは無邪気に笑い、うん! と頷いた。
―――――
うっかり怪談チックになってしまった…。ヌシ酒は何故茶色いのか、というお話(捏造)でした。

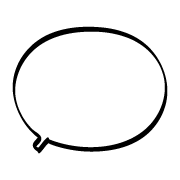


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です