「貴女、私のマスターの所に来ることになったから」
お使い妖精の彼女が私の入っている檻の前で、両手を腰に当てながら言い放った。
気まぐれな妖精は一度、店主についって行くと逃げ出すまで売られる運命だ。
それは私もよく分かっていた。
「じゃあ、ここから早くだしてくれない? 」
私がそう言って微笑むと、彼女は一瞬だけばつの悪そうな顔をした。
どうしてそんな顔をするのか、なんて聞いている暇もなく私は檻から出されて、荷馬車に乗せられた。
舗装されていない道を道行く住人より少し早いスピードで進む。外を眺めると、お使い妖精がパタパタと空を飛びながら小さな荷物を持ってお店を行ったり来たりしていた。
「ねえ、次に私のマスターになる人ってどんな人なの」
私は座ったまま、両手で頬杖をついて道を眺めながら彼女に聞いた。
土埃を上げながら、馬車は進んでいく。先ほどより、少しお店の数が減ったように見えた。
「マスターはいい人よ」
振り向くと、彼女は口元に笑みを浮かべたまま、睫毛を伏せていた。うっとりとした様子というのだろうか、なにか昔の懐かしい思い出を思い返しているようだった。
「で、そのマスターはラム酒を作るの?」
私はため息をついて、また道を眺める。今はもう街を抜けて森の中を進んでいた。
「作るわ」
彼女が強く断言する。そして、私の隣に座った。二人で少しの間、黙ったまま流れゆく風景を眺めていた。
「……さっきはごめんね」
「なにが?」
「始めが肝心だって先輩に言われたから、あんなに強く言ってしまって」
「ああ、あの来ることになったからって言い放った事?」
「そう……」
彼女の方をみると、少し泣き出しそうな顔をしていた。
「先輩妖精に、最初は強気で行きなさいって言われからやってみたんだけど、失礼な事しちゃったなって」
両手で顔を抑えた彼女を見て、私は慌てた。
「大丈夫だから、ね」
こんなところで泣かれても私は困る。思った以上に彼女は繊細な妖精だったようだ。
「もう、貴女も妖精の端くれなんだから、しっかり胸を張って前を見なさい」
「え……」
彼女は顔を上げて少し驚いた顔をした。
私は彼女を刺激しないように優しく微笑む。
悩むことがあったとき、その背中を押したり励ますのは先輩妖精の役目だ。
店に所属する妖精はどうなのか知らないけど、私たち気まぐれな妖精はそうやって、いろいろな人からアドバイスを貰って生きてる。
「いい? 私たち妖精は好きに生きていいのよ。貴女も飽きたら私たちのように気まぐれな妖精になりなさい。自由に生きていいんだから」
私は随分昔に先輩妖精に言われた事を思い出しながら、彼女に精一杯伝えた。
喋るのは好きだけど、伝えるのは苦手だ。だけど、こうやって素敵な言葉を伝えていかなければ気まぐれに生きている意味もないのじゃないかな、と勝手に私は思っていた。
もちろん、ラム酒の技術もこっそりと皆に次の新しい子達にも伝えていくつもりだ。
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
『気まぐれな妖精のお話』3話
関連投稿
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3008 view
住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3008 view -
 住民売り考察日記㉒複数買いhaguruma / 2156 view
住民売り考察日記㉒複数買いhaguruma / 2156 view -
 住民売り考察日記⑭道の効果haguruma / 2291 view
住民売り考察日記⑭道の効果haguruma / 2291 view -
 住民売り考察日記⑬売れ行き変動haguruma / 2641 view
住民売り考察日記⑬売れ行き変動haguruma / 2641 view -
 とある住民売り店の手記haguruma / 3498 view
とある住民売り店の手記haguruma / 3498 view -
 ★屋外作業に関する考察 ②『地形資源で獲得量が変動する屋外作業』の獲得量の計算方法についてこいくちしょうゆ / 26945 view / 2
★屋外作業に関する考察 ②『地形資源で獲得量が変動する屋外作業』の獲得量の計算方法についてこいくちしょうゆ / 26945 view / 2 -
 とある農家から見た「海」メノウ / 4881 view
とある農家から見た「海」メノウ / 4881 view -
 【初めまして】創業1週間の農家です【失敗談紹介】ぷちゅ / 5664 view / 3
【初めまして】創業1週間の農家です【失敗談紹介】ぷちゅ / 5664 view / 3 -
 衝動値引き上げ実験レポート人参屋 / 4923 view
衝動値引き上げ実験レポート人参屋 / 4923 view -
 錬金とは闇コダック / 7734 view
錬金とは闇コダック / 7734 view
SOLDOUT2
ゲームシステム
攻略
アイテム・作業
業種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
花屋
職種
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王
店舗情報
その他
おすすめタグ
さらに表示
新着記事
おすすめ投稿
-
 住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3008 view
住民売り考察日記㉓複数買いhaguruma / 3008 view -
 住民売り考察日記㉒複数買いhaguruma / 2156 view
住民売り考察日記㉒複数買いhaguruma / 2156 view -
 住民売り考察日記⑭道の効果haguruma / 2291 view
住民売り考察日記⑭道の効果haguruma / 2291 view -
 住民売り考察日記⑬売れ行き変動haguruma / 2641 view
住民売り考察日記⑬売れ行き変動haguruma / 2641 view -
 とある住民売り店の手記haguruma / 3498 view
とある住民売り店の手記haguruma / 3498 view -
 ★屋外作業に関する考察 ②『地形資源で獲得量が変動する屋外作業』の獲得量の計算方法についてこいくちしょうゆ / 26945 view / 2
★屋外作業に関する考察 ②『地形資源で獲得量が変動する屋外作業』の獲得量の計算方法についてこいくちしょうゆ / 26945 view / 2 -
 とある農家から見た「海」メノウ / 4881 view
とある農家から見た「海」メノウ / 4881 view -
 【初めまして】創業1週間の農家です【失敗談紹介】ぷちゅ / 5664 view / 3
【初めまして】創業1週間の農家です【失敗談紹介】ぷちゅ / 5664 view / 3 -
 衝動値引き上げ実験レポート人参屋 / 4923 view
衝動値引き上げ実験レポート人参屋 / 4923 view -
 錬金とは闇コダック / 7734 view
錬金とは闇コダック / 7734 view

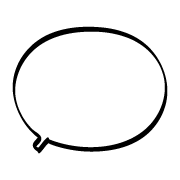


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です