森で出会った作業妖精の彼女に誘われ着いて行ったが、結論から言うと売られた。
彼女のマスターはラム酒を作るために彼女に地図の探索を命じていたが、途中で気が変わったらしい。彼女は最後まで私を売ることに抗議してくれていたけど、私が売られても良いと言ったのだ。
暗い倉庫に閉じ込められて、いつくるか分からないラム酒作りの機会を待ちながら、ぼんやり過ごすのはもう嫌だった。
私たち気まぐれな妖精は自由と娯楽、そしてそれを維持できるだけのお金持ちを好む。閉じ込められているだけなんて、四肢が腐り落ちるようで嫌気がさすのだ。
売られることを容認する代わりに、買う側にもそれなりの対価を支払ってもらう。それが私たちの娯楽でもあるラム酒作りだった。
「仕方ないわね……」
そう言いながら、店先に並べられた木製の檻の中から、道行く人々を眺める。
「本当に、ごめんなさい」
彼女は申し訳なさそうな顔をして、頭を下げた。
「貴女のせいじゃないわ。どこのマスターだってこうやって私たちを店先に並べるもの」
私がそう言うと、彼女は今にも泣きだしそうな困ったような表情を浮かべた。
彼女はマスターに仕える身だから、私たちの自由と娯楽の意味を分からないかもしれない。
島の人達は私たちの事を“お金持ちが大好きでほいほいついていっちゃう”そんな簡単に騙せそうな妖精だと囁いているけれども、そんなことはない。
確かに、お金持ちを愛してはいるが私みたいにこうやってマスターに仕える妖精から説得されてついていく子もいる。
お金持ちを見つけたら、追いかけて勝手についていくわけではないのだ。
「水辺で遊ぶのも楽しかったけど、貴女に出会えて私はちょっと楽しかったのよ」
私は彼女に笑顔を向けた。嘘はついていない。どちらも、これからどう転ぶかも楽しいものだったからだ。
「本当に、ごめんなさい」
「もう、謝ってばかりじゃない。貴女にはマスターがいるのだから仕事をしなさい」
手を振って彼女を追いやる。
彼女は頷くと、一度だけ私の方を振り返って店内に消ていった。
それから、幾日も幾日も店先で道行く人々を眺めていた。
この店はどうやら食べ物や飲み物を扱っているらしい。ハーブティーやマンガ肉などが売られていて、店に立ち寄る人々は買った品々を抱えて嬉しそうに立ち去って行った。
もう、何日経っただろうか。一週間か二週間か、そろそろ私はここに居る事を飽き始めていた。
「もう、つまんない。ついて来るんじゃなかったな」
そうぼやいても、周囲の雑踏に言葉はかき消されていく。
人々からしたらこの檻は虫かごくらいの小ささで、時折こちらに気づく人もれば、全く気付かない人もいる。
大抵は後者で、気づいて手を振ってくる人には私も手を振り返して、リップサービスをしていた。
「ラム酒作りの時しか逃げ出せないから、辛いのよね」
少し、目を伏せてため息をついた。
落ち込んでいても仕方がないと顔を上げると、一瞬何か光るものが店の中に入って行ったのが見えた。
「あれは、もしかして妖精?」
気まぐれな妖精は街には絶対にやって来ない。という事は誰かの所のお使い妖精だろうか。
もしかしたら、ここから出ていけるのではないかと思い、私は心を躍らせた。
***
これ、長いお話になります。
ハーブ印

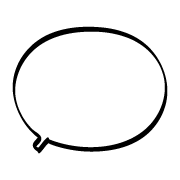


 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です