「失礼致します」
挨拶とともに扉を開け、その店の作業スペースに足を踏み入れた。
店頭にくらべると、そこは薄暗い。
その中心には、大きな水槽があり、その中身はぼろ布で隠されている。
ぼろ布の間からは10本の触手が伸びており、その先には……我々の知る概念に当てはめれば、これは作業妖精なのだろう。
作業妖精たちは、ただひたすらに枝に丸太に削り出し、楽器を作っていた。
笛、ギター、木琴、それに太鼓。私は音楽をやったことがないのでわからないが、きっとさぞよくできたものなのだろう。
見慣れない楽器もある。これは確か、バグパイプというやつか、遠い地方の郷土楽器だったと思う。
楽器作りの苦楽を聞こう。そう思って声をかけてみたのだが、そう…作業妖精たちから反応はない。(ふと思うと、そもそも、我々の言葉は通じるのであろうか?)
その代りに、水槽より応えが返ってきた。
いたって有効的な反応であった。だが、、、
「あの、いえ、すみません。」本能的ななにかを感じ、私はそそくさとその店を離れたのだ。
ことの始まりは、ただ楽器職人の取材を企画した、ただそれだけだった。
トパーズ村の住民より、島でも珍しいにっこり楽器職人がいる聞きつけここまでやって来たのだ。
気難しい職人か、それともファンシーでメルヘンな夢想家か、店主について様々な可能性を考えた。
この島には人間以外の店主も多い、姿が違ってもとくに何も無いだろう、そう思っていた。
だが、しかしだ、その実は、あまりに、言葉に表せないものであった。
あの水槽はなんだ。なぜ中身が隠されている。なぜ水槽中から明瞭な声を聞き取ることができる。すべてに対して理解を拒んでしまう。
ぼろ布から除く眼光は、けして冷たいものではなかった。間違いなく友好的な存在のそれである。なのに。
そもそもだ、店頭の妖精さんに話はつけてもらっていた。取材は快諾してもらった。そこから考えても友好的だ。すべての要素がウェルカムだった。
しかし、私は、恐怖に負けた。極めて失礼なことをしてしまった。取材側として、完全に失格である。
『私は何者か、なんのためにここに来たのか』
私は自分に問い、心を強いて奮い立たせ、踵を返した。
扉をノックする。
「先程は大変失礼いたしました。もしよろしいのであれば、再び取材させていただきたいのですが」
私は、持てる限りの勇気を右手に込め、扉を押し開いた。
それが良くなかった。
何が失礼しますだ大バカ野郎、本当に礼を尽くすなら、相手から許しがあってから開けるべきだ。
そんなこともわからなかった失礼者の私への、天罰だったのかもしれない。
扉を開けた先にあったのは、中心にある大きな水槽だ。
水槽からは10本の触手が伸びており、ぼろ布はかけられていなかった。それは店主の配慮だったのだ。
次に気がついたとき、私は店頭に運び出されており、妖精さんに介抱してもらっていた。
扉越しに、震える声で三度めの謝罪を告げた後、私は逃げ出した。
覚悟もなく、思慮も足りない、失礼者の私は、取材者失格である。
.
.
著者のコメント
猫目石さんの記事(https://soldout2.secretary.tokyo/articles/1cdf9e9f6e439c9)に触発されて、当店の日常を書こうと思ったはずなのになにか違うものになったぞ!
でもまあ、日常ってほんとに楽器作ってるだけだから、ほとんど書けてるし、まあいっか!![]() (
(![]()
![]()
![]() )
)![]()

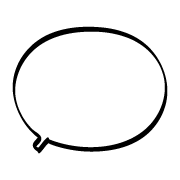




 ログインが必要です
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です